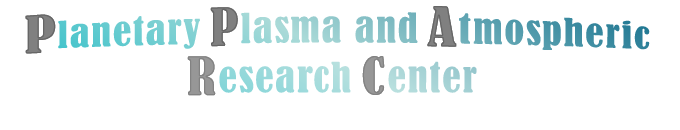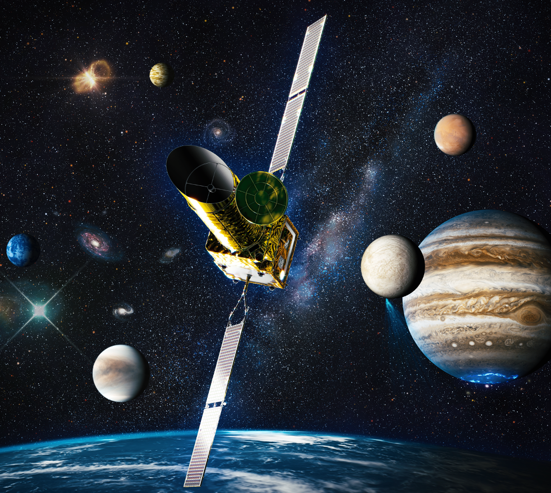火星をテーマにした研究紹介
火星(かせい、英: Mars)は、地球軌道の外側を公転する地球型惑星です。現在の火星表面は乾燥していますが、水が流れた跡のような地形が多数存在しており、太古の火星は豊富な海と温暖な気候を持っていたと考えられています。現在はその海は失われ、火星表面の大気圧は地球の1/150程度ですが、極地には氷やドライアイスの氷冠が、大気には雲が存在し、時には大気が地表の砂塵を巻き上げるダストストームが発生しています。過去に存在した火星の水や大気はどこに消えたのか?火星大気の現在の気象現象はどのように駆動されているのか? 現在の火星の観測から、これらの手がかりを得ようとしています。
MMXは、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が進める火星探査ミッションで、2つの衛星「フォボス」と「ダイモス」の起源を調べ、フォボスの表面から試料を採取して地球に持ち帰る計画です。打ち上げは2026年、地球帰還は2031年を予定しています。この探査によって、火星の衛星の起源を解明し、太陽系の進化の理解が深まることが期待されます。
MMXには複数の科学観測機器が搭載されており、そのひとつであるMIRS(MMX赤外分光計)は衛星の表面から放射される赤外線を分析して、鉱物や氷などの組成を調べ、フォボスの起源や物質の分布を詳しく知る手がかりを得るとともに、火星の大気の観測を行います。
東北大学はMIRSの開発に関わるとともに、MIRSが観測する火星大気の赤外分光データから火星の気象現象を調べる解析手法の開発を行なっています。
宇宙科学研究所MMXプロジェクトページ
Illustration by JAXA
極端紫外線分光器を搭載し、世界初の惑星観測専用に設計された宇宙望遠鏡です。2013年9月に打ち上げられ、2023年12月に運用を終了しました。
この間、金星や火星といった地球型惑星の大気と太陽風の相互作用を調べ、木星の衛星イオから流出するプラズマを観測することにより、太陽系内の地球型惑星の大気進化や、木星磁気圏プラズマの起源とプラズマを加熱するエネルギー源を調べる研究を進めました。
貴重な観測データを使った惑星の研究は現在も進行中で、東北大学を含め、世界の最前線の研究の場で活用されています。
see details
LAPYUTAは、宇宙科学研究所・公募型小型計画のプリプロジェクト候補として検討を進めている紫外線宇宙望遠鏡計画です。宇宙の生命生存可能環境(目標1)と宇宙の構造と物質の起源の理解(目標2)を目指し、以下の4つの科学目標、(1)太陽系内天体の生命生存可能環境, (2)地球型系外惑星の大気,(3)近傍銀河の形成過程,及び(4)宇宙における重元素の起源、を掲げて検討を進めています。
これらの科学目標を達成するため、水素、酸素、炭素の輝線を含む110-190nmの真空紫外波長域で、高い空間解像度と波長分解能を持つ紫外線宇宙望遠鏡の開発を進めています。打ち上げ目標は2033年です。東北大は望遠鏡および観測装置の光学設計と科学検討の両面でこの計画を主導しています。