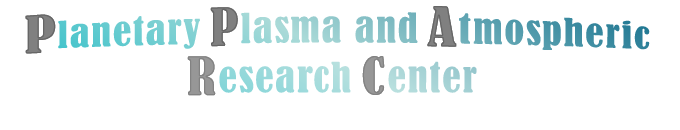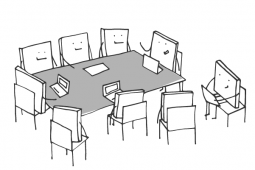PPARCセミナー (2025/10/17)
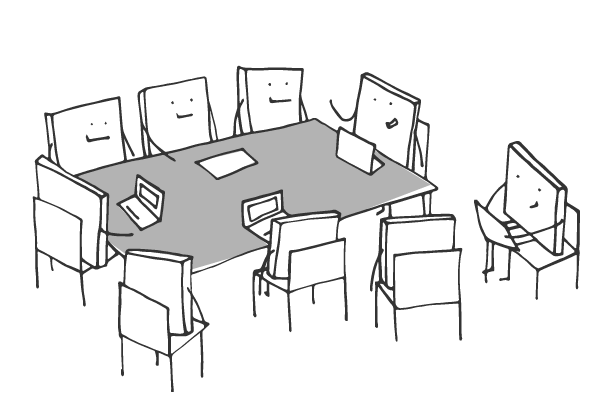
PPARCセミナー (2025/10/17)
(1)
[Name]
Rentaro Sugawara
[Title]
Junoのwaves/dataを用いた木星nKOM放射の半自動解析手法の開発と初期統計解析
[Abstract]
木星狭帯域キロメートル波放射(nKOM)は、イオプラズマトーラスを起源とする電波であり、その放射特性は木星磁気圏のプラズマ環境を反映している。先行研究ではnKOMの基本的な放射特性が明らかにされてきた一方で、イベントの抽出精度に加え、放射が示す長期的な変動を明らかにすることも重要な課題であった。そこで本研究では、より客観的な基準でnKOMイベントを抽出し、その長期変動を解析するための基盤を構築することを目的として、独自の半自動解析手法を開発した。
本手法では、ダイナミックスペクトルから、周波数帯や狭帯域性といった特徴に基づきnKOMを目視で同定する。その後、開発したコードを用いてイベントの発生期間を自動で抽出し、データベース化する。この手法をJunoの初期のデータに適用し、得られたカタログから放射強度と磁気緯度の関係を調べた。その初期結果として、低緯度帯において、放射のピーク位置に南北非対称性を示唆する傾向が見られた。
本セミナーでは、開発した半自動解析手法の概要と、それを用いて得られたnKOM放射の緯度分布に関する初期的な特徴を報告する。
(2)
[Name]
Keiya Kawagata
[Title]
UHR 電子密度データ更新後のArase 衛星における衛星電位ー電子密度の相関
[Abstract]
最近 Arase 衛星における UHR(高域ハイブリッド共鳴波動)周波数を用いた電子密度は全面更新され、その信頼性が大きく向上した。このデータを
用いて、衛星電位―電子密度の相関について低エネルギー電子データも併せた再評価を行った。
Arase 衛星は、2017 年 3 月以降、約 7 年間に渡りジオスペースを飛翔し、この領域の電子密度・温度決定に資する多様なデータを取得し続けている。
密度・温度は電離圏・プラズマ圏・磁気圏の構造を決める基本情報であり、波動の分散関係やその成長・減衰、伝搬経路をも左右する。Arase 衛星で
は、PWE/HFA(プラズマ波動計測器/高周波受信部)の電場スペクトル(10 kHz~10 MHz)から UHR 周波数を自動判定と目視の組み合わせで
同定し(時間分解能:1 min)、背景磁場強度と併せて電子密度を決定してきた。この方法は、電子計測器(LEPe)の下限エネルギー (2017/5 以降:
37 eV) の低温成分を含む電子密度を高精度で決定できるが、UHR 周波数近傍に他の強い波動が見られる領域や UHR 強度が弱い低密度領域の場合
にはその決定は難しい。他衛星ではプラズマ密度として低エネルギーイオン・電子の直接計測データが併用されてきたが、粒子計測器では低温粒子の
検出が難しい。特に内部磁気圏域では低温プラズマが多く、Arase の静電プラズマ計測器 LEPe・LEPi では計測対象にならない低エネルギーの分布
関数に仮定が必要となる。
衛星電位も電子密度の指標となる。プラズマ中における衛星の浮動電位は、太陽紫外線による光電子流出と周辺プラズマからの電子流入のバランスで
決定される。衛星表面材料に依存する光電子流出・二次電子放出効率、衛星の形状・姿勢、および周辺電子温度に影響されることから、衛星電位から
演繹される電子密度の精度は低い。しかし、目視決定や特定の仮定に依存することなく 1-spin(8 sec 程度)の分解能で観測量を取得できるため、光
電子放出が無い日陰時を除き、ある程度の信頼性を持った電子密度を導出することが潜在的に可能であり、また低エネルギー電子の温度情報も推定で
きる可能性がある。
これまで、Arase 衛星は 1 /cc 以下(電子プラズマ周波数:~10kHz 以下)で、UHR 由来電子密度の精度が低く、衛星電位との相関が過剰に悪く見
えていた。幸い、UHR 電子密度データは 2024 年に全面更新され、より信頼性が高くなった。本研究では最新電子密度データ(2017 年 4 月~2024
年 12 月)を用いて、衛星電位―電子密度の相関について低エネルギー電子データも併せた再評価を行った。
はじめに、衛星電位と UHR 電子密度との相関について再評価を行った。具体的には、MLT を 8 つに分割し、それぞれの領域での UHR 由来電子密
度―衛星電位の相関およびその経年変化の確認を進めている。これまでこの相関は低密度域(1 /cc 以下)で過剰にばらついていたが、電子密度デー
タの全面更新に伴ってかなりの収束をみた。特に hot 電子の少ない昼側では、log(電子密度) と衛星電位の間によい精度を見出している。とはいえ、
hot 電子の多いプラズマ圏外・夜側では、依然として低密度域でこの関係から逸脱し、想定される相関よりも衛星電位が小さく出るデータが散見され
る。プラズマシートの影響で電子密度がより高くなる夜側ではより流入電子電流量が大きくなることがあり、衛星電位がより下がってバランスするこ
とによると考えうる。
この検証に向け、LEPe による~37eV 以上の電子の密度・温度モーメントデータを併用し、プラズマ温度が与える衛星電位への定量的な影響評価に
着手した。光電子電流量に影響しうる太陽 UV flux との相関も確認予定である。
プローブ電位の安定度は、磁気圏・電離圏電場及び低周波電場波動の精度決定要因でもある。本研究は、2026 年から周回観測を開始する
BepiColombo/Mio 水星探査機における同型プローブを用いた電子密度・電場計測の精度保障の基礎ともなる。Arase 衛星・Mio 探査機はアンテナ
長が 15 m と短く(Geotail・Cluster:50 m)、低密度域で Debye 長>アンテナ長となりやすい。このため、プローブ電位が Debye 長以内の「周辺
プラズマ電位より衛星電位に近いポテンシャル」を拾うことで、擬似的に低衛星電位にみえる可能性もある。これまで Arase 衛星はプローブに与える
バイアス電流量を光電流流出量の~50% 程度に抑えて運用してきたことも、この影響を助長している可能性がある。2025 年 6 月からは光電流流出量
の~80% 程度にバイアス電流量を向上させており、UHR 由来電子密度データが更新され次第この評価も進めていく。